カテゴリー
- ALL
- Media
- Press
- Insight & Opinion
- Event
- Apple Vision Pro

- Media
「ベンチャー.jp」にて代表小林のインタビューが掲載されました
起業家のための情報メディア・ベンチャー.jpにて、MESON代表の小林のインタビュー記事が掲載されました。
June 16, 2025
NHK放送技術研究所様主催の「技研公開2025」にて、ARグラスを活用した未来の視聴体験のコンセプト展示に協力いたしました
2025年5月29日〜6月1日に行われた、NHK放送技術研究所様主催の「技研公開2025」にて、ARグラスを活用した未来の視聴体験のコンセプト展示に協力いたしました。
June 5, 2025

「Blackbox」にて、代表小林のインタビューが掲載されました
日本のスタートアップシーンをグローバルに発信するメディア・Blackboxにて、MESON代表の小林のインタビュー記事が掲載されました。
April 16, 2025

東京ガス様の『FlexiViewer』活用事例がMac Fan 2025年5月号に掲載されました
東京ガス様の『FlexiViewer』活用事例がMac Fan 2025年5月号に掲載されました。
March 28, 2025

- Media
- Insight & Opinion
東洋経済オンラインにて、デロイトトーマツコンサルティング様との対談インタビューが掲載されました
東洋経済オンラインにて、MESON代表の小林とデロイト トーマツ コンサルティングの稲葉 貴久氏の対談記事が公開されました。
March 25, 2025

- Media
- Insight & Opinion
「XR Life Dig」にて代表小林のインタビュー記事が公開されました
NTTコノキューデバイス様が運営するメディア「XR Life Dig」にて代表小林のインタビュー記事が公開されました。
March 25, 2025

- Media
「住宅新報」にて『FlexiViewer』が紹介されました
2025年3月19日(水)の住宅新報にて、『FlexiViewer』が紹介されました。
March 19, 2025
.png)
- Press
MESON、次世代3Dプレゼンテーションツール『Immersive Pitch』を発表
MESONは、次世代3Dプレゼンテーションツール『Immersive Pitch』を開発し、2025年3月1日~2日に中国、上海で開催された展示会「LET’S VISION 2025」にて発表いたしました。
March 5, 2025

- Press
MESON、Apple Vision Pro向け3Dモデルビューワー『FlexiViewer』のトライアル版をリリース
空間コンピューティング技術を活用した体験デザインとプロダクト開発を行う株式会社MESON(東京都渋谷区、代表取締役社長:小林佑樹、読み:メザン、以下MESON)は、Apple Vision Pro向け3Dモデルビューワー『FlexiViewer』のトライアル版をApp Store上でリリースいたしました。
February 5, 2025

- Press
- Apple Vision Pro
都市における空間メディアの可能性広がる LEDディスプレイとApple Vision Proを連動させたコンテンツをSTYLYとMESONが共同制作
空間コンピューティング技術を活用した体験デザインとプロダクト開発を行う株式会社MESON(東京都渋谷区、代表取締役社長:小林佑樹、読み:メザン、以下MESON)は、株式会社STYLY(東京都新宿区、代表取締役CEO:山口征浩、以下STYLY)とともに、LEDディスプレイとApple Vision Proを連動させたオリジナルコンテンツ「404 AQUARIUM」を制作しました。
December 26, 2024

- Event
Developers Summit 2025にCTO比留間が登壇します
2025年2月13日~14日にホテル雅叙園東京にて開催されるDevelopers Summit 2025に、CTOの比留間が登壇します。
December 25, 2024

- Press
MESON、「NVIDIA Omniverse Partner Council Japan」へ参画決定
空間コンピューティング技術を活用した体験デザインとプロダクト開発を行う株式会社MESON(東京都渋谷区、代表取締役社長:小林佑樹、読み:メザン、以下MESON)は、NVIDIA社が結成したNVIDIA Omniverse Partner Council Japan に参画しましたことをお知らせいたします。
December 18, 2024
View More

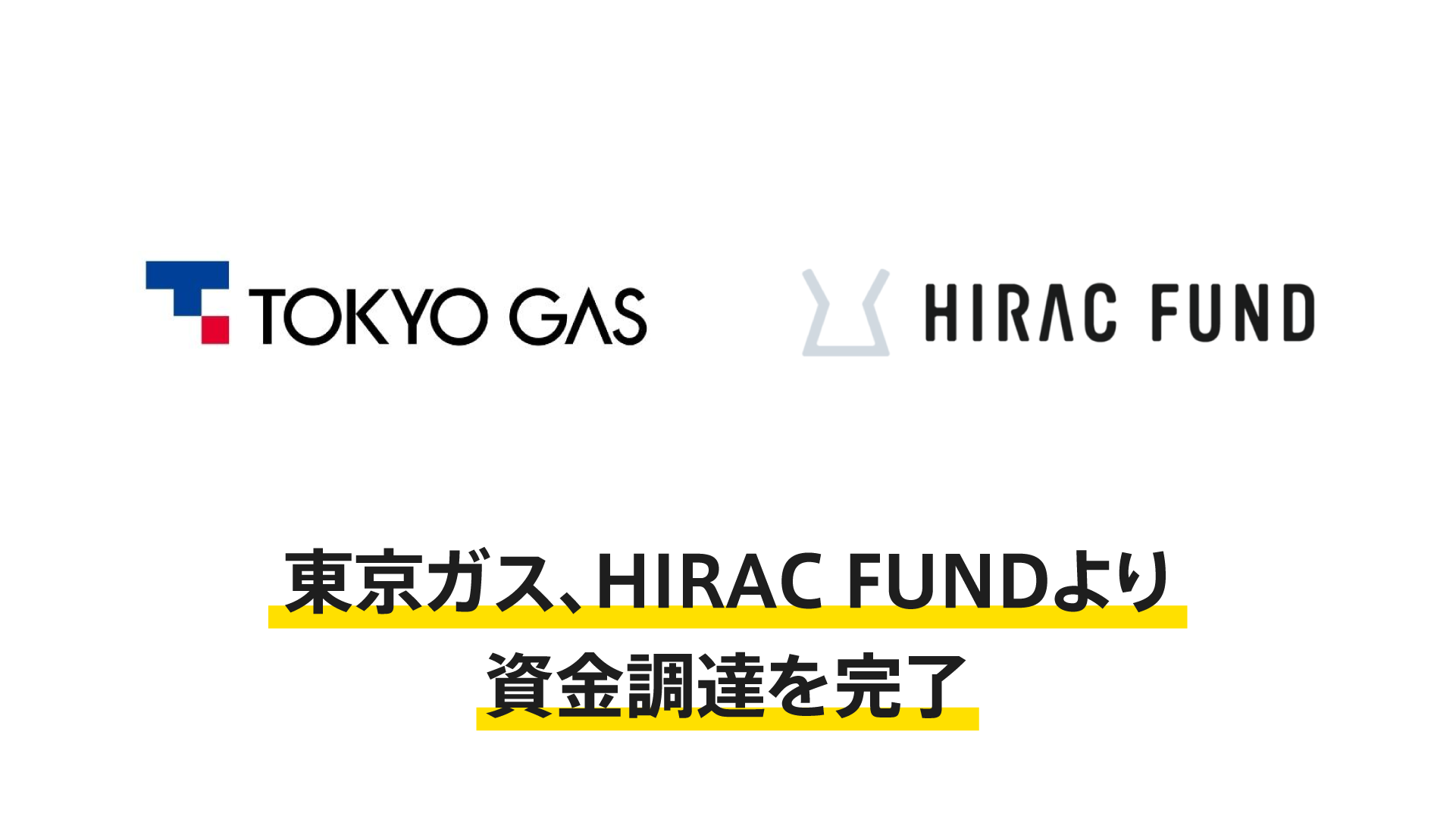

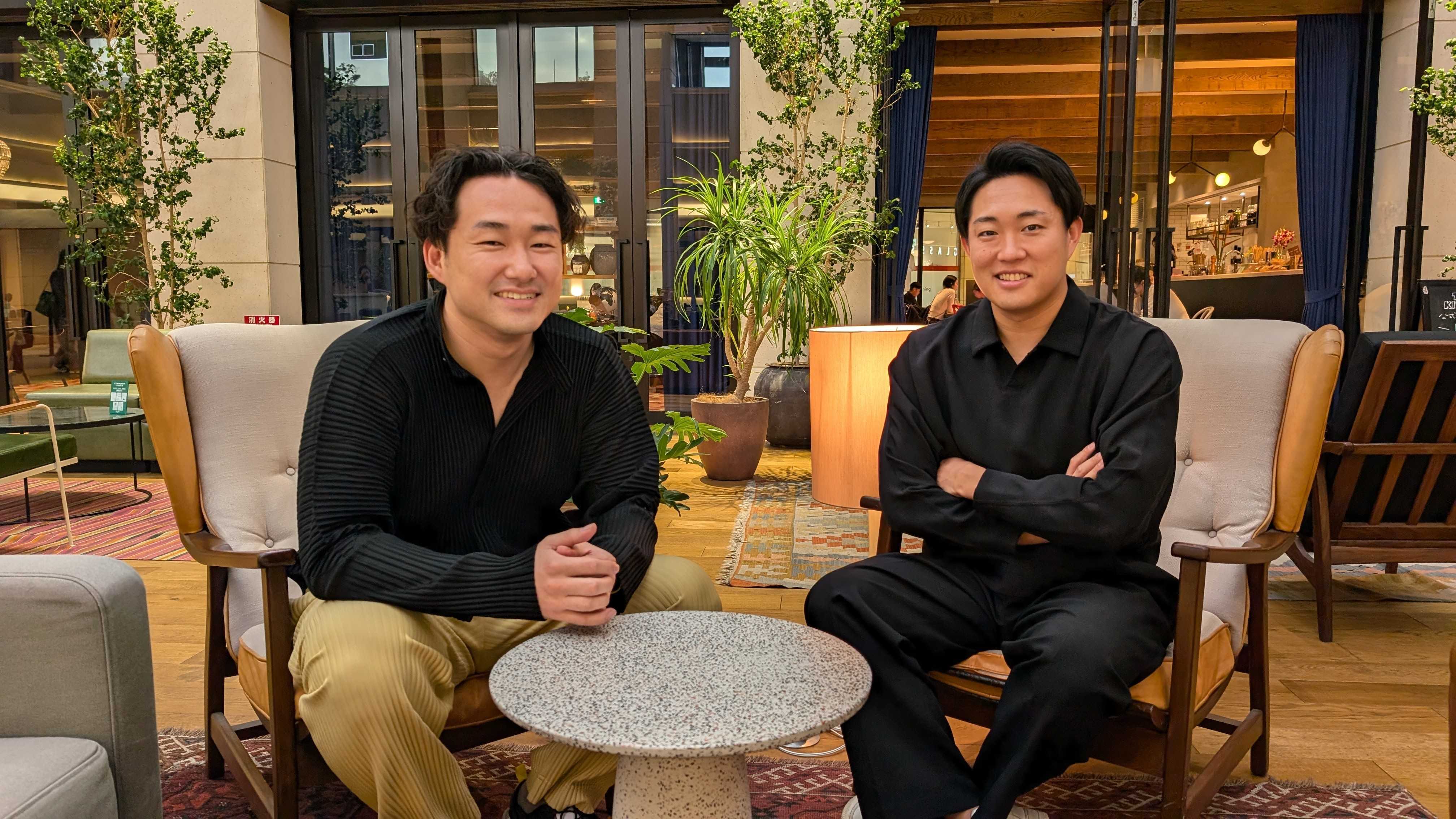

.png)


