- Apple Vision Pro
- Design
- Partners
「想定以上」のアウトプットはなぜ生まれたのか。イトーキの事例に学ぶ、本質的な課題解決を実現する空間コンピューティング活用術
August 28, 2025

オフィス、教育機関、公共施設。人が集い、働き、学ぶあらゆる空間を、家具というハードウェアと、長年培った知見というソフトウェアの両面からデザインする株式会社イトーキ。彼らのビジネスの根幹は、顧客の課題を深く理解し、最適な空間を提案することにある。
しかし、その提案の現場では、長年一つの大きな壁が存在していた。それは、まだ存在していない空間の価値を、いかにして提案の場で顧客に「自分ごと」として体感してもらうか、という課題だ。
この根深い課題に対し、イトーキはApple Vision Proという最先端のテクノロジーでブレークスルーを試みた。MESONとの共創で生まれた「SMART CAMPUS tour」は、単なる技術デモに終わらず、顧客の心を動かし、ビジネスの未来を照らす確かな手応えをもたらしたという。
プロジェクトを牽引した株式会社イトーキ スマートキャンパス推進部の宮前氏に、開発の背景から得られた知見、そして空間提案の未来まで、詳しく話を聞いた。
■「見せた方が早い」――空間提案の現場が抱え続けた、もどかしい壁

――まず初めに、宮前さんのお仕事について教えてください。
宮前氏: 私は2007年にイトーキに入社し、開発から商品企画、プロダクトデザイン、営業まで、空間提案に関わる様々な職務を経験してきました。現在はその経験を基に、スマートキャンパス推進部に所属し、デジタル技術を活用して、主に大学キャンパスなどに向けた空間DXの提案を行っています。
――宮前さんが空間提案の領域で抱えていた、業務上の課題についてお聞かせいただけますか。
宮前氏: 我々の仕事はお客様のニーズに合った空間を提案することですが、関係者が多くなるほど、その合意形成は難しくなります。例えば、コロナ禍を経てニーズが大きく変化した教室の空間提案を例に挙げると、授業を行う先生、学ぶ学生、そして施設を管理する方と、それぞれの立場から多様な要望が出てきます。
感染拡大を防ぐために、リアルとオンライン、両方の環境を一つの教室内に整備しなくてはならないという新たな前提も生まれ、これらのニーズに応える形で教室内の家具を自由に再配置し、目的別の空間を構築できる「ハイフレックス型学習環境ソリューション」を現在展開しています。
ただ、家具の再配置によって変わる空間の価値を各ステークホルダーに共有していくプロセスは、非常に難しいものでした。
――完成前の空間を説明する場面では、主に建築パースや図面などが使われるのでしょうか。
宮前氏: はい。しかし、それらの二次元の情報だけでは、最終的な空間の広がりや雰囲気、使い勝手といった体験価値を伝えきることに難しさがあると感じていました。いつも議論の最後には、「結局、実際に見せた方が早いよね」という結論に行き着くんです。ものすごく頑張って説明はするのですが、やはり実物を見ていただく体験にはかないません。

最も有効なのはショールームにお越しいただくことですが、そこでも課題はありました。お客様にご提案しているドンピシャの製品が展示されているとは限らないため、「これは色違いです」「今は執務空間での利用を想定した展示をしていますが、今回はエントランス用にご提案させていただいています」といった補足説明が必要になり、お客様の頭の中で情報を補完していただく手間が発生します。それが提案しているプランとお客様のイメージの間にギャップを作る要因になっていました。
■「本物と見間違える」ほどの衝撃。Apple Vision Proとの出会い

――その長年の課題を解決するブレークスルーとして、空間コンピューティング技術に注目されたのですね。
宮前氏: そうですね。転機となったのは、2023年にMESONさんのオフィスでApple Vision Proを体験したことです。これまでも様々なVRゴーグルを試してきましたが、Apple Vision Proの体験は比べ物にならないほどハイクオリティでした。MESONさんが開発した『SunnyTune』というアプリや、浅草で撮影されたイマーシブビデオを見せていただいたのですが、そのリアルさに「なんだこれは」と。
――従来のVRデバイスとは、何が決定的に違ったのでしょうか。
宮前氏: 映像の解像度、そして現実空間とのシームレスな融合ですね。特に驚いたのは、現実の机の上に置かれたバーチャルなオブジェクトに、本当にそこにあるかのように、ふんわりと自然な影が落ちていたことです。そのリアルさは、「本物と見間違えるんじゃないか」と思えるほどでした。
ここでの体験が、我々の提案のあり方を変える可能性を秘めているのではないかと考えるきっかけとなり、その可能性を具体的な形にするべく、今回MESONさんとの取り組みを開始するに至りました。
■「これで提案してほしい」――現実とバーチャルが繋がった、新しい顧客体験

――その確信から今回の取り組みがスタートしたのですね。よろしければ、改めて「SMART CAMPUS tour」について教えてください。
宮前氏: 「SMART CAMPUS tour」は、イトーキが提唱する、リアルとオンラインを融合させた新しい教室「ハイフレックス教室」の価値を伝えるためのコンテンツとして開発しました。
単にVR空間を歩き回るだけでなく、まず家具の3Dモデルとスライド型の説明画像でハイフレックス教室のコンセプトを理解し、次に教室全体のミニチュアモデルで空間構成を俯瞰し、最後に実寸大の空間に没入して利用シーンに応じたレイアウトの変化を一人称視点で体験する、という多層的な構成になっています。
さらに、プロジェクターで体験内容を投影できる仕組みを構築することで、体験者以外にも広く価値を理解していただけるような工夫もしました。

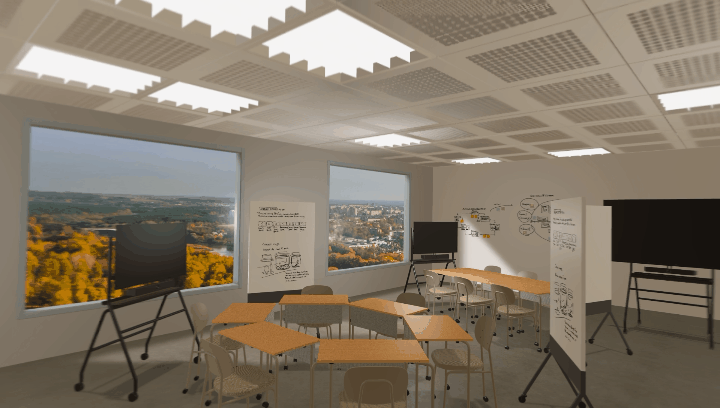
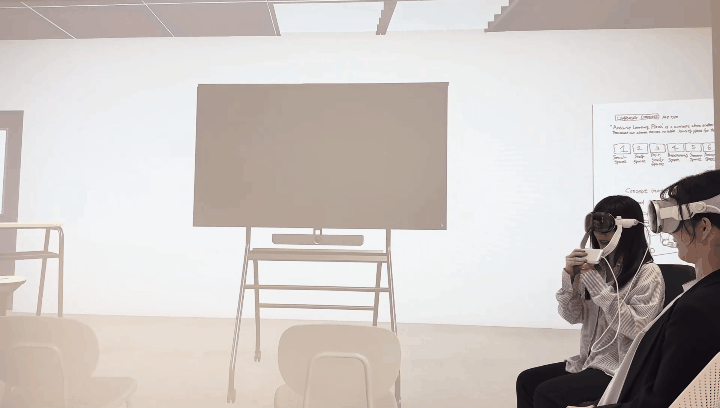
――教育関係者向けに行われた展示会での展示が最初の舞台となりましたが、来場者の反応はいかがでしたか?
宮前氏: 期待を大きく上回るものでした! 特に多かったのが「これを持って提案に来てほしい」という声です。展示会に来られるのは、必ずしも最終的な決裁権を持つ方ばかりではなく、最終的な決定権者へ説明するための資料を作成しなければならない方の場合が多いのですが、そういった方々から、「これがあれば、自分たちが苦労して資料を作らなくても、一度体験してもらうだけで価値が伝わるのに」と言っていただけたのは、大きな収穫でした。
――展示会場で、特に印象的だったエピソードはありますか?
宮前氏: 体験者の方が、ご自身が座っている現実の椅子と「SMART CAMPUS tour」内で見えている椅子が同じだと気づき、「あ、これって今座っている椅子ですか?」と尋ねられた瞬間ですね。こちらが説明する前に、お客様の中で現実の体験とバーチャルな体験が地続きになった。現実のモノの質感や存在感を活かしながら、デジタルの力で可能性を拡張できることに、空間コンピューティングならではの大きな手応えを感じました。
また、エンドユーザーである学校の先生方が、色やテクスチャなどの家具の仕様ではなく、「こうやって家具を動かして教室を使うのね」と、空間の運用や使い方という本質的な価値に着目してくださったのも、プロジェクトの成功を示す出来事だったと思います。我々が本当に伝えたかったメッセージが、ターゲットに正しく届いたと感じました。
■なぜMESONの提案は「想定以上」だったのか
――今回のプロジェクト成功の裏には、MESONとの密な連携があったと伺っています。
宮前氏: まさにその通りです。実は、私が最初にMESONさんにご相談したのは、もっとシンプルな「VRウォーキングシミュレーター」のようなものでした。Meta QuestやHoloLensで過去に何度も試した、いわば手慣れた手法です。
しかし、MESONさんは私の要望をそのまま受け入れるのではなく、「宮前さんや営業の皆さんは、どのように空間提案を行っていますか?」「イトーキ様のお客様に、どんな価値を伝えたいのですか?」と、より本質的な問いを投げかけてくれました。クライアントである我々の、さらに先にいるお客様の視点に立っている。その視座の高さに、まず驚かされました。
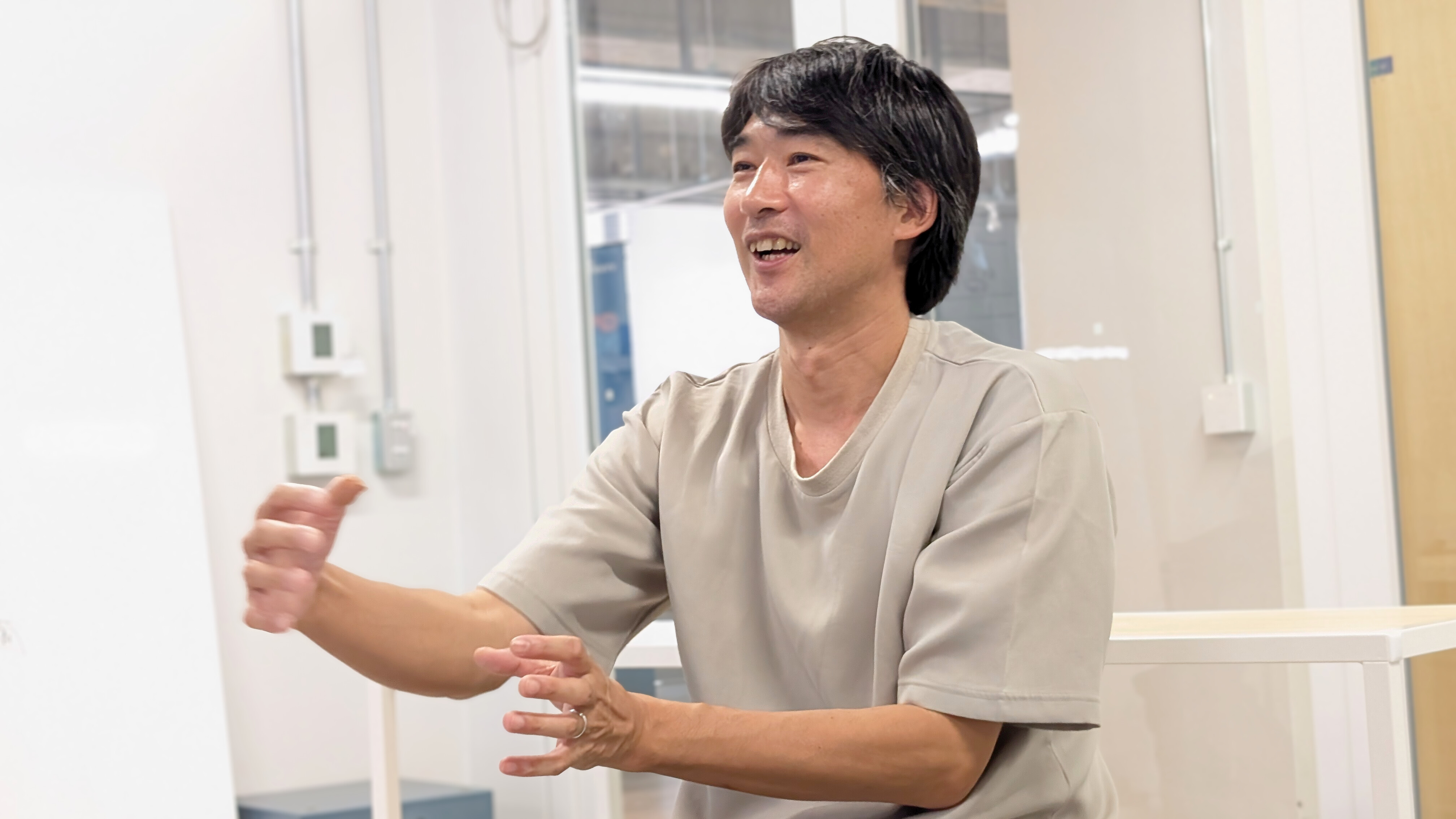
――その問いから、新しい体験デザインが生まれたのですね。
宮前氏: はい。深いヒアリングを経て、単に歩き回るだけではない、現在の多層的な体験デザインが生まれました。私自身、後から振り返って「VR一辺倒では、我々が大事にしている現実空間の価値が出てこない。MESONの提案は正しかった」と気づかされました。
最初の打ち合わせで、2Dのスライドを使った紙芝居のような形式で体験の流れを説明してもらったのですが、その時点で完成形がありありとイメージでき、すぐに「これだ」と。いい意味で、もうどうなるかが分かってしまったんです。
――プロジェクトの進行はスムーズでしたか。
宮前氏: 開発期間は非常にタイトで、正直に言えば「残り時間的に絶対に無理だろう。よくこの仕事を受けるな」と思っていました(笑)。しかし、この初期提案の精度が非常に高かったおかげで、その後の進行は驚くほどスムーズでした。クライアントである僕らですら想像していなかった、「想定以上」のアウトプットを提示してくれた。そこにこそ、今回MESONさんとご一緒した本質的な価値があったと感じています。
■営業プロセスを変革する、空間コンピューティングという新たな選択肢
――今回の取り組みは、今後の営業活動にどのような変化をもたらしそうでしょうか。
宮前氏: 非常に強力な新しい選択肢が加わったと考えています。空間コンピューティング技術を活用すれば、お客様先にいながら自社のショールームに匹敵する、あるいはそれ以上の納得感を得られる体験を提供できる可能性があります。
例えば、お客様から「サンプルの椅子を持ってきてほしい」と依頼されたとします。私たちはその椅子を1脚だけお持ちし、実際に座っていただく。そのリアルな体感を持ったままApple Vision Proを装着いただき、「この椅子を30脚並べた教室の様子がこちらです」とバーチャル空間をお見せするんです。
――まさにリアルとバーチャルの「いいとこどり」ですね。
宮前氏: 実物で担保されたリアリティがあるからこそ、バーチャル空間の説得力が格段に増すんです。バーチャルコンテンツに懐疑的な方からよく言われる「どうせ本物とは少し違うんでしょう?」という疑念を、最初に実物に触れてもらうことで払拭できる。これは非常に強力な営業手法になるはずです。バーチャルとリアルが地続きになった延長線上にある「体験」を届けることで、高い納得感を持っていただきながら、よりスムーズな合意形成が行えると感じました。
■実空間×空間コンピューティングの可能性
――今回の取り組みを経て、宮前さんご自身の考えに変化はありましたか?
宮前氏: 「実空間をいかにうまく使うか」という視点が、これまで以上に重要だと再認識しました。これまでは現実の代替としてVRを捉え、いかにリアルに再現するかに注力していました。しかし、今回の共創を通じて、それは正しいアプローチではなかったなと。
重要なのは、現実とバーチャルを対立させるのではなく、いかに融合させ、相乗効果を生み出すか。実空間をハブとして、XRコンテンツでその価値を拡張していく、という考え方に変わりました。
――今後、空間コンピューティング技術の新たな活用イメージはありますか?
宮前氏: 最も可能性を感じているのが、我々のショールームそのものの体験を拡張することです。例えば、お客様が単品で展示されている椅子に興味を持たれたとします。そこでApple Vision Proを装着いただくと、その椅子が実際に使われている教室の空間がミニチュアで表示され、次に一人称視点で目の前に広がり、そのまま没入して体験できる。
また、実物では伝えきれない機能性を、バーチャルで補うことも可能です。例えば、スタッキング(積み重ね)可能な椅子が1脚だけ展示されている場合、Vision Proをかざすと、バーチャルで椅子が複数現れて、実際に積み重なる様子を立体的に見せることができる。カタログの写真だけでは伝わらない省スペース性などを、直感的に理解していただけるはずです。
――この記事を読んでいる企業の方々へ、メッセージをお願いします。
宮前氏: 色々とお話させていただきましたが、結局のところ、この体験の価値は「やらないとわからない」というのが結論です。情報を収集し、頭で理解することももちろん大事ですが、それだけでは本当の可能性は見えてこない。まずは一度、ご自身の目でこの新しい世界を体験してみてほしい。この記事を読んでいる場合じゃないですよ、と伝えたいですね(笑)。
――まさしくその通りですね!今日はお話いただき、ありがとうございました!
